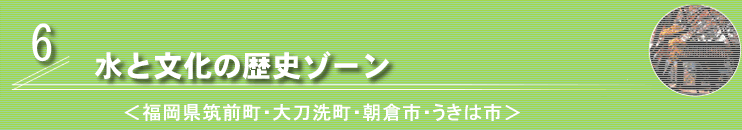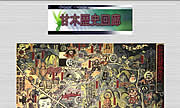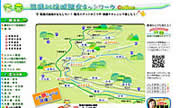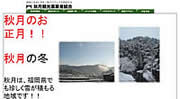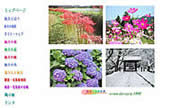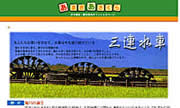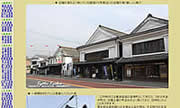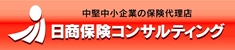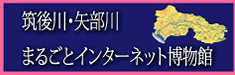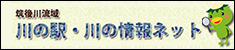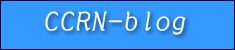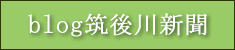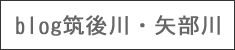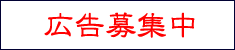筑後川の水は、現在でこそ、農業用として利用されているけれども、江戸時代に筑後川四堰(袋野堰−水没、大石堰、山田堰、恵利堰)が作られるまでは用水としては利用できなかった。
筑後川の水は、現在でこそ、農業用として利用されているけれども、江戸時代に筑後川四堰(袋野堰−水没、大石堰、山田堰、恵利堰)が作られるまでは用水としては利用できなかった。
このゾーンでは、江戸時代からの祖先たちが築いた利水技術が今も継承されている。特に、山田堰は江戸時代の姿をとどめて、山田堰から水を引く朝倉の三連水車は300年を超えて今なお使用されている。
原鶴温泉や筑後川温泉では、鵜飼も楽しめる。また、このゾーンはブドウ、カキ、ナシ、リンゴ、イチゴなどの果物の産地であり、観光農園も点在する。棚田でも有名である。
標高889mの古処山を水源とする豊かな水は、この地に和紙、草木染、淡水のり、葛など独自で文化的な産物を生み出した。江戸時代は黒田藩の支藩秋月藩がおかれたところであり、秋月城跡やそのまわりに武家屋敷が残り、城下町の風景を残している。さらに弥生時代中期から古墳時代にかけての大規模な多重環濠集落、平塚川添遺跡があり、弥生時代の生活を体験できる公園となっている。
 川茸・スイゼンジノリ
川茸・スイゼンジノリ(三奈木&蜷城散策)
http://www.geocities.jp/
hr_shiromizu/amagi/minagi/
buzenbou/kawatake/kawatake.htm